 |
 |
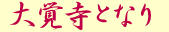
だいかくじとなり |
|
当サイトは『よそ見』と『歩きによる寄り道』を信条としているとはいえ、基本的に引っ込み思案で人見知りする筆者は、道を尋ねる以外では他人様に声をかけるなどという行為はまずしない。
まして人の出入りが少なそうな店はヘンな気を遣ってしまうので見送ることが多い。
だが世界的観光地でありながらも往来の少ない道で、しかも一般民家にしてはなんとも独特な雰囲気の看板が目に付いた。
パッと見には、春風に開け放たれた引き戸に掛かった暖簾も珍しくはない。京都には染色とか工芸品などを売っているお店にはこうした雰囲気の所が多いのでさほど気にもとめない。
しかしその左にある金の浮き彫り看板は、ちょっとした寺の山門にでも懸かっていそうな程の立派さだ。
しかも玄関の傍らにはすごく凝った作りで、かなり上等なタペストリーに見えるのに、それにしてはずいぶんフツーの垂れ幕のように陽や風にさらすが如く掲げてある。その真偽を確認しようとおそるおそる近づくと、もちろん印刷などではないし、広告の仕事で使ったりする布対応の大型インクジェットの産物でもない。それどころか、大劇場の緞帳(どんちょう)を連想させるような重厚な作りなのだ。
|
|
もういちど入り口の左に目を移すと、『友遊結』───“ゆう、ゆう、ゆう”と読ませるのだろう。その下に『きもの着付け、和裁』とも。
何屋さんなのだろうか。
失礼ながら、あまりのアンバランスさに筆者の好奇心に火が付いた。玄人の手によるものなのか、文字としては味があるものの、デザインレイアウト的には素人と思われる『小さな小さな美術館 ちょっと道草しませんか!』の文字に引き込まれるように入り口へ近づいていった。
その時の筆者の脳裏には、暖簾をくぐってみると上手にお歳を召した小さなおばあさんが座敷の奥にちーんと座って「よお、おこし」と言ってくれそうな光景が浮かんでいた。
|
 |
|
|
 |
| だが、あにはからんや、暖簾に触れるかどうかのタイミングで「どうぞどうぞ、お上がりください」とハリのある声で迎えてくださったのは和服姿も粋な、老舗旅館の女将を思わせる凜とした雰囲気の実に上品なご婦人だった。
そして目に飛び込んできたものは部屋の奥に所狭しと置かれたきらびやかで巨大な工芸品の群れ!
この際だから正直に書くと、以前、町屋を改造して営んでいるとある工芸系の店の入り口に二階で『着物と染め物展やってます。お気軽に』とあったので、西陣や三条あたりのアトリエでやってるような作家展のギャラリーかと上がってみると、しっかりフツーの呉服屋さんがフツーにセールをやっていて、そのばつの悪さに即座に踵(きびす)を返した経験があったので、すわ、さてはこれも美術工芸品を売ってる店だったのかと恐れをなした。
だが、ぜひ作品の説明したいからと実に熱心に仰るので、その異様なほどにゴージャスな作品の近くに寄りたい欲求もあってズカズカと上がらせていただいた。もちろん疑り深い筆者はいわゆる骨董品のキャッチセールスの類ではなかろうか、と一抹の不安を覚えていたが、脱水するまで逆さに振ったところで美術工芸品などは欠片すら購入できそうにもない筆者の風体を見た上で座敷へ上げてくださるからには、無駄とご承知の上だったのだと思うことにした。
ショウケースなしで眺めるのさえも恐れ多そうな作品群を遠巻きにしていたら「もっと近寄って見てください」と仰る。それでも万一のことがあってはいけないので、脚がもつれてもかわせるだけの距離を保って眺めてみて驚く。
衣紋掛けに下がっているのは間違いなく袋帯である。だが、左のはともかく右のデカいのはタペストリーかと思っていたら、これは『丸帯』といって、両面使えるいわばリバーシブルの帯なんですよ、教えてくださった。
男性諸氏はまず判るまい。袋帯というのは振袖や留袖…いや、それさえも呉服屋さんの広告に携わる以前の筆者なら皆目理解できなかっただろう。要するに『いっちゃんゴージャスな着物に使う工芸品のような高価な帯』である。
だが触感はまるで開発初期のGORE-TEXか大昔のテント生地みたいにゴワゴワしていて、生地としてはとんでもなく重い。金糸銀糸を使ったり、織りと染めを複雑に組み合わせて糸一筋ひとすじをチマチマと組み立てるようにして作られる。だからなまじな外車なら即金で買えて釣りまであるほどの値段になる品物もザラにある。
それでもピンキリで、一般的な袋帯では複雑な刺繍や柄は一部分にしか施さない。なぜなら、締めてしまえばほとんど隠れてしまって見えるのはごく一部、しかも締める度にこすれて傷むだけだからだ。
だがご覧のようにこれらは上から下まで源氏絵巻風の細工が施されている。しかも、右のはそれが倍の面積になっているのである。さらに、それぞれ金色の部分は漆塗りの『蒔絵(まきえ)』における盛り上げ技法を応用して描かれているので金の部分は立体的に膨らんでいるのだ。つまりこの帯はこすれて消耗する部分にさえ惜しみなく細工がされているという、とーんでもなく贅沢な作品なのである。
|
|
|
|
|
 |
なにやら説明だらけになってしまって申し訳ないが、それほど我々には縁遠い世界の彼方からこの作品群はやってきている。
これらの作品を描かれたのは『島田えり茂(しまだえりも)』と仰る、来年60歳になられる作家さんだそうだ。
作品を紹介してくださった女将さん(…というのは変なのかも知れないが、館長さんというのも妙だし、リーフレットによるとたぶん岸本さんとおっしゃるのだと思うが、お名前を確認しなかったので確認が取れるまではこの呼称でお許し願おう。
───さらにお許しを請うついでといっては何だが、お姿も撮影させていただいたにもかかわらず、人物写真になれない筆者は緊張から露出をミスってしまって使えない写真しか撮れなかったので掲載を見合わせた。誠に面目ない)のお話によると、本来は西陣織や京友禅に独自の技法で金彩や金蒔絵、さらには金箔を施した創作をされているようなのだが、とにかく素材はもちろん、技法も題材もこだわることなく気さくに何でも、何にでも描かれるのだそうな。
そんな例がこの瓢箪(上段中央のは本体高さだけで60センチはあっただろうか)に描かれた仏画や七福神だったり、漆の板やら木綿のハンカチやら、ほんとに気の向くままに描いておられるようだ。ある種、マテリアルの実験をされているようでもある。
事実、作家として独自の世界を持っていながらも、この女将さんの要請で一般的なイラストレーターの作品の模写を訪問着に描かれていたりするのである。これには驚いた。
伝統工芸に携わる作家さんというのはえてしてそういう事には高いプライドをお持ちだと勝手に思っていたからだ。
|
|
さらに女将さんの発案による、いわば“お洒落な作務衣(さむえ)”というコンセプトの新時代の着物も制作されているそうだ。ちなみに左の女性用、下は巻きスカートなのだとか。だけど柄は友禅染め、しかし生地は木綿。なのに肩に描かれたアクセントの絵は一流作家が描いた金蒔絵仕立て。
別な意味で超ゼイタクなのだ。例えが悪くて申し訳ないが、感覚的には棟方志功が自宅便所の壁に落書きをした天女図みたいなものか。
和服、それも友禅や西陣織はまさに歩く美術絵画だとあらためて実感した瞬間である。
美しいものに浸り、満ち足りた気分で一般住宅ならではの急な階段を下りてから玄関先に掲げてあった写真を見ると、島田氏と演歌歌手の香西かおり氏とのツーショット。
06年、07年と彼女の紅白歌合戦における衣装を手がけたのが島田氏だったのだ。さらには、現役横綱時代の若貴兄弟の写真も。そう、化粧まわしである。そうか、やはりアレはこういった作家さんが手がけているのかと納得した。
ちなみに龍のモチーフが多いのは、島田氏の夢のひとつが巨大寺社の天井画を描くことだからだそうな。これも納得。だが金泥を使った龍の天井画は数あれど、蒔絵や盛り上げ金漆を施したものなどあっただろうか。ほの暗く広大な寺の天井にぎらりと煌めく金の目、金のウロコ。これはぜひ観てみたいものだ。
このあと二階へも上げていただいた。二階では着付け教室もされるので巨大な鏡がしつらえてある。お客様はいなかったとはいえ、仕舞ってあった着物をいとも気さくに広げて見せてくださった事にも肝をつぶした。
だが、二階で見せていただいた作品は、着物も帯も一階のゴージャスな工芸品とはがらりと趣を異にし、友禅らしい上品な美しさに満ちていた。
もちろんそれらにも島田えり茂氏ならではの技法でさまざまな手を加えてある。
|
 |
|
 |
残念ながらこれも写真がないのだが、特に印象深いのは群鶴図(ぐんかくず)と呼ぶのだろうか、青鷺が水辺に群れる絵柄の青系の美しい訪問着と、同じモチーフでありながら銀糸をちりばめたシルバーベースの袋帯のコーディネートには見惚れた。もちろんこれにも要所要所に金蒔絵技法を使ってある上に、これまた氏が工夫された特殊な方法で螺鈿(貝類の真珠質部分を極薄の板状にしてモザイク画のように使う技法)が施されていた。まさに、着る工芸品。
和服、それも友禅や西陣織はまさに歩く美術絵画だとあらためて実感した瞬間である。
美しいものに浸り、満ち足りた気分で一般住宅ならではの急な階段を下りてから玄関先に掲げてあった写真を見ると、島田氏と演歌歌手の香西かおり氏とのツーショット。
06年、07年と彼女の紅白歌合戦における衣装を手がけたのが島田氏だったのだ。さらには、現役横綱時代の若貴兄弟の写真も。そう、化粧まわしである。そうか、やはりアレはこういった作家さんが手がけているのかと納得した。
ちなみに龍のモチーフが多いのは、島田氏の夢のひとつが巨大寺社の天井画を描くことだからだそうな。これも納得。だが金泥を使った龍の天井画は数あれど、蒔絵や盛り上げ金漆を施したものなどあっただろうか。ほの暗く広大な寺の天井にぎらりと煌めく金の目、金のウロコ。これはぜひ観てみたいものだ。
|
|
|
|
これだけヤイヤイ書いていて肝心の着物の写真が少なくて申し訳ない。というのも、常識的に作家の一点ものやギャラリーでの写真撮影は御法度だからだ。しかし女将さん曰く、この『大覚寺となり』さんはもともと商売度外視で、島田えり茂という作家の活動を広く知らしめたくて営んでいる『美術館』だから…とのこと。
それならと、おそるおそる『ぶら旅』での紹介の許可を求めたら、大変喜んでくださったのである。こんなことなら二階で拝見した見事な着物もバシバシ撮れば良かったと悔やんだが、そう言えば絶対に一旦片付けた着物をまた広げてくださるに違いないので今回は見送った。
実は店内(というのもこれまた妙だが)には女将さんだけでなく、一階の工芸品の前では若い女性が友禅染の作業をされていたし、二階は二階でほくほくした笑顔の女性が着物の手入れをされているところだった。
突然のちん入者に仕事の邪魔をされ、しかも儲けに繋がるどころかむしろ貧乏神みたいな筆者にもイヤな顔ひとつせず、「ありがとうございました」と見送ってくださったのである。
上の写真は逆に一般的な黒漆の板に桜を“なんとなく”描いたという一種の“壁飾り”。ある意味、着物など本来の素材に転用するための習作といえるかもしれない。
これを読まれた着物好き、工芸好き、そしていろんな話を聴くことが好きな好奇心一杯のアナタ。ぜひ嵯峨野を訪れたならちょっとフシギなこのお家へ足をお向けなさい。
きっと、嵯峨野散策に幸せな想い出の一ページになるはずだ。
外へ出ると、春の陽射しと暖かな風が気持ちいい嵯峨野の田園風景が待っていた。
|
|
|
|
▼『大覚寺となり』付近の地図はこちらから▼
|
|
|
 |
 YahooIDをお持ちの方は YahooIDをお持ちの方は
ここからご希望の携帯電話へ
マップ情報を転送できます。→■ |
|
|
|
|
|
|
|
|